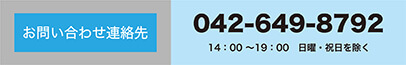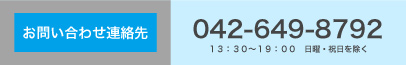■晴れの日に傘を貸して、雨の日に傘を取り上げる
これはバブルが吹っ飛んだ頃に銀行をはじめとした金融機関に対して、皮肉を込めてよく言われていた言葉ですね。調子がいいときには銀行の方から頼み込んででもお金を借りてもらいに来たのに、調子が悪く少し左前になった途端に強く返済を迫られたり、貸しはがしにあったなんて会社がそこかしこに溢れていましたね。
私たち学習塾の業界でも、似たような話はあります。
例年、他塾の受験生で2学期以降に私を訪ねて相談にこられる生徒、保護者の方が必ず2~3組はあります。その内容は一言で言えば、「助けてください」ということですね。
3年間通って、入試が遠くにある時期には「大丈夫ですよ」、「頑張ってますよ」なんて聞こえのいいことばかり言っていたのに、志望校の合格を獲りにいこうとするこの時期になって「無理です!志望校は2ランク下げてここにしなければ責任はもてません」とか、ひどい場合は「おたくの○○君は基礎基本から出来ていないんですよね」だって・・・。この子、3年間ちゃんと授業料払って通ってたんですよ。
要は、これって高い授業料をとって「勉強ごっこ」をさせていただけなんですよね。前にもこのコラムに書きましたが、上位難関といわれる学校で合格を勝ち取ろうとした場合は、内申基準のみの推薦入試でもぐり込むケースを除けば、そういうレベルの教科指導を受けていることが不可欠なんです。これなくして受験させるのは、木の棒一本でアメリカ海兵隊に戦いを挑むようなものです。
だから、出来るだけ早い時期に大まかな形でもいいので、志望校や進路のイメージを作っておいて、そのための準備をする。たったそれだけのことなんですよね。もちろん、入学試験は相手があることですから、その準備を怠りなくやったからといって必ず合格を手にできるとは限りませんが、問題の出方一つで「勝ち負け」というところまでは持っていけるとは思います。
であるのに、そういった指導もせずに長い期間子供たちをあずかり、授業料を受け取り、しかも一番肝心なところではリスクをとらない。こちらのほうが経営としては効率的なんでしょうが、まさに晴れの日に傘を貸して、雨の日に傘を取り上げるようなものでしょう。これではその学習塾の存在意義を問われますよね。
私は、学習塾や予備校なんてものは、本来なくてもいいものだと思っています。というより、正規の教育機関が子供たちの学力の下支えと伸長を機能的に果たすことが出来るのならば、ないほうがいいとすら言ってもいい。だからこそ、私たちは少しでも有意義な存在でなくてはならないと強く思います。さらに、そこに通う生徒と保護者にとって「他を以って代えることの出来ない場所」にならなければ、そこに存在する価値はないでしょうね。
Takahide Kita